はじめましてねんちょうさん①
公開日: 2025年9月15日月曜日
こんにちは。本校で生活科を担当しております芦原と申します。本校3年目となりました。今年度も1年生を担任しています。
昨年度、生活科を軸に約半年間をかけて附属幼稚園との交流を行いました。今年度も引き続き取り組む予定です。
年長期(5歳児)から小学校1年生の2年間までの「架け橋期」は、生涯にわたる学びや生活の基盤をつくる上で重要な時期であり、この時期の教育を充実させることが課題となっています。令和4年度からは19の自治体がモデルとなって「幼保小の架け橋プログラム」の取組を推進しており、全国的な「架け橋期」の教育の充実が目指されています。
しかし、「各幼児教育施設・小学校において、連携の必要性について意識の差がある」「形式的な交流活動にとどまり、カリキュラムの改善・実施が行われていない」「指導方法の見直しがされていない」といったことが、課題として挙げられています。(中央教育審議会初等中等教育分科会「学びや生活の基盤をつくる幼児教育と小学校教育の接続について~幼保小の協働による架け橋期の教育の充実~」令和5年(2023)2月)
そこで、年長児との継続的な関わりを通して関係性を築いていく中で、相手の立場に立って考えることや互いに歩み寄ることの大切さを感じ、自分自身の成長とともに相手のよさに気付くことを目指したいと考えました。構成としては、半年間をかけた大きなプロジェクトの中に、小さなプロジェクト(単元)を位置付ける形にします。そうすることで、年長児との関わりを深めていきながら、相手意識を明確にすることで、生活科における気付きの質を高めていくことをねらいます。
今年度は、昨年度年長児として交流に参加していた子どもたちが、1年生として関わります。昨年度と立場が変わった子どもたちとこれまでに交流をしたことのない子どもたちとが、どのように活動を進めていくだろうかと考えているところです。
さて、ここからは授業についてのお話をします。
最初に、子どもたちに「3月まで附属幼稚園の年長さんといっしょに生活科をやってみない?」ということを提案しました。附属幼稚園出身の子どもたちは、入学前からたのしみにしている子どももいたのですが、それ以外の子どもたちは「え、年長さんは生活科できるの?」「附属幼稚園じゃなかったから分からない」といった反応でした。(ちなみに、クラスで年長のときに交流を経験したことがある子どもは2名しかおらず、「一度だけ小学校に行って、遊んだり授業のことを教えてもらったりした」とのことでした。)そこで、昨年度の写真を提示した上で、附属幼稚園出身の子どもたちに、交流について話してもらうことにしました。
T:ひろしさんは、何か言いたそうな顔をしているね。年長さんだったとき、1年生とどんなことをしたの?
ひろし:1年生が迷路とかをつくって、遊ばせてくれた。秋の物とかどんぐりとか、葉っぱとか使って。
かなみ:どんぐりのこまもあった。
CC:他に貨物列車もした!
CC:おにごっこ!氷おに!
(これら以外にも、ブランコ、鉄棒、スクーター、砂遊び、ジャングルジム、虫取り等たくさんの遊びが挙がりました。)
T:でも、附属幼稚園じゃなかった人たちは、まだよく分からないんだよね?じゃあ、去年何をしたのか、聞いてみる時間にしようか。
ということで、附属幼稚園出身の子どもたち2~3人ずつとそれ以外の子どもたちを組み合わせてグループをつくり、去年の交流について尋ねる時間を取ることにしました。
どのグループでも、何をして遊んだかということについて話をしていました。「1年生といっしょに遊んだ」ということが一番印象に残っていたようでした。それ以外では「写真に〇〇ちゃんが写っているけれど、何をしているんだろう?」と、疑問を口にする様子もありました。
その日の振り返りでは、
「たのしそう。でも、話はよく分からない」
「ちょっとよく分からないけれど、遊ぶのはたのしそう」
「たのしそう。思い出になりそう」
といった記述が多くありました。交流のことはまだよく分からないけれども、話を聞く中でたのしそうな雰囲気を感じたようでした。一方で、少数ですが「年長さんが『やりたい』と言ったことをやろう」と「『(1年生が)また来てほしい。また遊びたい』と年長さんに思ってもらえるようにしたい」と考えている子どもたちもいました。
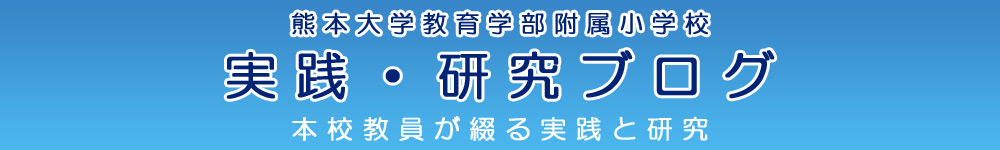

0 件のコメント :
コメントを投稿